年を増すごとに、省エネ基準が厳しくなる日本。2025年4月には全ての新築住宅に「省エネ基準適合」が義務化されます。2050年にはZEH水準の基準が引き上げられる予定ですね。
やっと北欧の基準値(トップクラス)に近づいてきている昨今ですが、
なぜ住宅の省エネ基準値がどんどん高くなっているのか・・・
知れば知る程、大事な事だと気づく”省エネ”ですが、
一体何が省エネにつながるのか難しく、わからないですよね。
日本の省エネ基準値と、省エネの基礎について一緒に学んで行きましょう!
住宅の省エネ基準は?

国土交通省の『建築物省エネ法』で定められています。
国の省エネ基準『建築物のエネルギー性能向上に関する法律』とは・・・
・2050年のカーボンニュートラル
・2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)
上記の2つの実現に向けて、2021年10月地球温暖化対策等の削減目標を強化する事が決定されたのです。
これを受けて、日本のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組を急がなくてはならなくなりました。
国土交通省の建築物省エネ法のページはこちらです。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html
わかりやすく言うと・・・
1、住宅の断熱性能を上げる事により、高気密高断熱となり冷暖房の効率が良くなり、光熱費も削減出来る!⇒温室効果ガスの排出削減にもつながり、自然エネルギー(資源)の削減にもつながります。
2,家の性能を上げると室内の温度差が低減されるため、従来の部屋ごとの温度差が高い性能の住宅よりヒートショックなどの人体への負担も軽減出来るようになる。⇒人体にも優しい!
3,住宅ローンの金利優遇や、もらえる補助金の幅が増える※申請時期や地域により違います
良い事づくめ!だと思われがちですが、当然初期費用という観点からは当然従来通りとはいかなくなります。30年住めれば十分・・・という家の創り方や考え方ではなく、省エネ基準に適合する住み良い住宅を作り、住み終わってもリフォームして永く住める住宅作りを考えていく時代となったのではないでしょうか。
先を見越して投資する・・・
3R(スリーアール※リユース・リデュース・リサイクル)の観点からも考えていくべき時代・・・とも言えます。
では実際家を建てる時にどのような基準ならば許可されるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
2025年住宅の省エネ適合基準とは・・・
1,住宅の断熱等級と呼ばれる、断熱性能の数値で表した基準の数値が4以上の住宅
2,一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
上記2項目を満たす住宅でなければならないという基準です。
断熱等級とは・・・?
断熱等級の正式名称は『断熱等性能基準』で、等級1から等級7まであります。
数字が大きい程良くなる基準値です。この数値が4以上が2025年度の省エネ基準となります。
・等級5は少ない冷暖房で過ごせる家・・・2030年には義務化されるであろうZEH基準
・等級6は冷暖房を付けなくても快適に過ごせる高い基準の省エネ住宅
・等級7は断熱等級4から40%ものエネルギー削減が見込める最上級の省エネ住宅
いづれにしても、住宅のUA値を算出する事により算出できるのが断熱等級となります。
そして、地域によっても基準値が違うのが特徴です。それもそのはず、日本も風土により環境が違うためですね。
建物を建てたい地域によって、寒い地域(北海道など)は区分1~4、暖かい地域(関東など)は区分5~6などと決められています。
国土交通省の地域区分新旧表はこちらです。https://www.mlit.go.jp/common/001500182.pdf
お住まいの地域によって違い、同じ県でも少し寒い区域は地域区分が下がっているので、ご確認ください。
UA値(ユーエー値)(W/㎡・K)とは?
正式名称は『外皮平均熱貫流率』ですが、外皮から逃げる熱の総量を床面積で割り求めます。
そして、このUA値を低くすることにより、断熱等級が良くなるのです。
UA値が低い程、住宅から熱が逃げずらい住宅=省エネ住宅という判断となります。
一次エネルギー消費量等級とは?
一次エネルギー消費量等級とは、1年間に消費するエネルギー量を表す指標です。
UA値を算出した後に計算できるのが一次エネルギー消費量であり、算出したUA値を元に、付加要素である設備の省エネ数値などを入力する事により算出出来る数値です。
一次エネルギー等級4とは具体的にどのくらいのエネルギー?
一次エネルギーを計算すると、BEIという数値によりエネルギー削減率が算出されるのですがそのBEIが等級を示す数値となります。
・等級4・・・BEI1.0以下
・等級5・・・BEI0.9以下
・等級6・・・BEI0.8以下
BEIの値が小さい方が、等級が高い住宅という事になります。
BEIとは・・?
Building Energy Indexの訳で、建築物の省エネ性能を評価する指標で、
⇒設計一次エネルギー消費量を、基準一次エネルギー消費量で除して求めます。
●基準一次エネルギー消費量とは・・・法令や基準に基づく建物の最大許容エネルギー消費量です。
●設計一次エネルギー消費量とは・・・建物の設計段階で予測されるエネルギーの消費量です。
これから建築する家が、効率的にエネルギーを使える家かどうか・・・排出ガスを減らせる省エネ住宅かどうかを客観的に知る指標と言えそうです。
最後にどうしたら住宅の省エネ基準値に近づけるのか、ワンポイントでご紹介します。
省エネ基準値を上げるには、窓の性能が不可欠!
窓といえば、ペアガラス!と言っていた時代は過ぎ去り、現在ではトリプルガラスも通常普及しています。
そして、空気層にはアルゴンガス入りが標準だったり、さらにはクリプトンガスの窓もあるんです。
ガラスの能力によっても左右されてしまう省エネ数値。
自然エネルギーをより利用して、冬場の電気代を削減するガラスの性能までもこだわる事が省エネの性能の向上につながります。
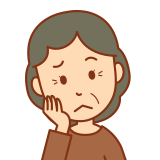
え?ガラスも選べるの?
従来だと、ペアガラスで、枠はアルミサッシより樹脂サッシ方が良い…なんて聞いた事はあるのではないでしょうか。
現在は、アルミと樹脂を融合させた枠によるサッシ性能の差があり、各種サッシメーカーでも複数のランクを設けています。
効率的にエネルギ‐ーの消費が出来るのが、冬の日差しを多く取り入れられるように南の窓を大きく、そして日射熱取得型のガラスにする方法です。
また、サッシの枠が薄く、性能の良いサッシを導入し、太陽エネルギーを取り込みやすくした設計とする事も重要です。
もちろん、太陽光エネルギーを再利用する「創エネ」と呼べれる太陽光発電を取り入れた住宅がZEH基準となるので、その省エネ基準が最終目的ですが、次項以降で一緒に勉強していきましょう。
まとめ
住宅の省エネ基準は?窓の性能が重要?省エネ住宅のポイントをわかりやすく解説と題して、住宅の省エネ基準について、要点をまとめてお伝えしました。
いかがでしたか?省エネ住宅に住み、地球にも、身体にも優しい住まいを手に入れたいですよね。
各項目については、次項で詳しく説明していきたいと思います。

